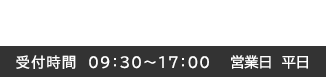A. 相続税の税務調査で 調査官が特に注目するポイント は主に下記のとおりで、申告漏れを防ぐために重要です。
1.財産の把握と名寄せ
被相続人および相続人の銀行・証券・貸金庫等の通帳や取引履歴(過去5年間程度)を確認し、
記載漏れや不自然な金銭移動(名義預金など)がないか調査されます。
たとえば子名義の口座に親の資金が振り込まれていないかも確認されます。
2.生活実態との整合性チェック
被相続人の預金残高の減少状況が生活費として妥当か、
また相続人の収入に見合った預金増減があるかなど、生活実態に照らして財産の移動状況が合理的かどうか見られます。
3.生前贈与・名義預金の確認
年間110万円以上の贈与(暦年贈与)の未申告や、贈与契約書の作成有無、
名義預金の判定など、適正な贈与税申告がされているか、深掘りされます。
4.相続財産の評価方法と漏れの有無
不動産、証券、美術品、貸付金、法人株式などの評価が妥当か。
また、自宅・不動産の名義、固定資産税の負担実態なども照合されます。
5.相続人・被相続人の背景や経緯
職業や学歴、趣味、生活費、趣味、介護費用の実態、預金管理者、生前の資産形成の経緯などについての聞き取りが行われます。
たとえば専業主婦の奥様の財産について、誰がどのように築いたか質問されるケースもあります。
調査の全体イメージ(ストーリー形式)
① 税務署から「申告内容の確認をしたい」と連絡を受ける
② 自宅などで午前に聞き取り(相続人・被相続人の経歴や資産形成など)
③ 午後に書類の検証(通帳・証拠書類の提示)
④ 調査官が不審点をまとめ、指摘事項を整理して終了。約1日がかりです。
調査されやすいケースの例
相続総額が2億~3億円以上と大きい
預貯金が多い、貸付金などもある
複数の金融機関口座があり通帳の管理が不明確
税理士に依頼せず自己申告
死亡直前の大きな出金や生前贈与が多い
→ 上記は調査対象になりやすい典型例です。
まとめ
税務調査では、相続人・被相続人含めた
資産の流れ・所有実態・生活実態との整合性が重点的に調べられます。
特に生前贈与や名義預金、不動産や貸付金などの漏れに要注意です。
書類整備と事前対策が重要で、税理士の活用や整理された記録の備えがおすすめです。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。